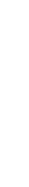熊本で多発するオオクロバエのシーズン到来!?危険性や対策方法について解説!(※閲覧注意)

熊本も秋らしい季節になりました。紅葉やスポーツ、食欲の秋と楽しみが多いですね。
一方、害虫駆除業者としては「気温が下がるからオオクロバエが増えるんじゃないか?」と思ったりして……
そして案の定、当店の現場でオオクロバエが多数捕獲されました。
「寒い季節にハエ?」と思われる方もいるかもしれませんが、オオクロバエは低温を好むため、秋から冬にかけて発生が目立つのです。
※この記事にはハエの画像が含まれるので、苦手な方はご注意ください。
1. オオクロバエとは
・分類:クロバエ科のハエの代表種。
・形態:体長は10〜12mmで割と大きめ、体は丸みを帯びている。
・色:青黒色。
・分布:日本全国。
・特性:低温を好む。
・発生源:動物の死骸や糞、生ゴミなどで繁殖。
現場での経験上、熊本市内での発生時期は11〜1月くらいではないかと思います。
阿蘇などの比較的冷涼な地域では、もっと早い時期から出没するかもしれません。

2. オオクロバエの危険性
① 衛生害虫としてのリスク
ハエ類は病原菌やウイルスを媒介するため、薬機法で「衛生害虫」に指定されています。
食品工場や飲食店では異物混入の原因にもなり、衛生管理上の大きな脅威です。
② 不快害虫としてのリスク
客席や施設内に侵入すると、利用者に強い不快感を与え、イメージダウンにつながります。
3. オオクロバエの捕獲事例
当店ではオオクロバエなどの大型のハエに対しては、捕獲器による駆除をメインに実施しております。
屋外に捕獲器を設置し捕獲駆除することで、屋内への侵入を未然に防ぐ手法です。
薬剤を使用して殺虫するのではなく、誘引剤(ハエの好む臭い)を使って捕獲するので人や動物、環境にも配慮した安全性の高い駆除方法です。
飲食店や食品工場、病院、物流倉庫など幅広い事業所での導入実績がございます。

下の写真は記事冒頭で触れたオオクロバエの捕獲状況です。
容器の中に見える黒い物体の多くがオオクロバエ等のハエ類ですが、12月も大量捕獲が続く可能性があります。

4. オオクロバエの発生対策
以下の対策をおすすめいたします。
① 侵入させない
ドアや窓を開けっ放しにせず、こまめに閉めることが大切。
換気を行う場合はなるべく網戸を利用しましょう。
秋〜冬は害虫が出にくいので、つい気が緩んでドアや窓を開放するかもしれませんが、この時期にオオクロバエの発生が増えるので、侵入口をつくらないようにしましょう。
② 発生源がないか確認する
オオクロバエの発生が目立つ場合は、周辺に繁殖源があるかもしれないので確認してみましょう。
繁殖はしていなくとも、生ゴミの臭いに誘引されて侵入することもあります。定期的に清掃を行うことが重要です。
③ 殺虫剤等で駆除する
市販のスプレー剤やハエ取り紙などを使って駆除しましょう。
【殺虫スプレーを使う場合】市販の殺虫・防虫スプレーの多くはピレスロイド系の有効成分を含んでいます。この成分は哺乳類と鳥類にはほとんど影響がありませんが、それ以外の生物群(爬虫類や両生類、魚類ほか)には有害です。特に水性生物への毒性が高いので、室内で魚などをペットにしている方はスプレー剤の使用にはくれぐれもご注意ください。
④ 害虫駆除業者に依頼する
施設の構造や立地等によっては、自力での防除が難しいケースもあります。
その場合は専門家に調査や駆除を依頼するとよいでしょう。
5. おわりに
オオクロバエは秋冬に活動が活発になる衛生害虫です。
食品関連施設や飲食店では、衛生管理と顧客満足の両面から早めの対策が欠かせません。
当店では捕獲器を用いた駆除サービスをはじめ、施設特性に合わせた防除プランをご提案しています。
「この時期にハエが増えて困っている」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。